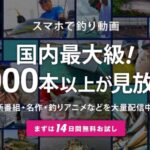イワシはさまざまな魚のベイトとなっています。
そのため、イワシをエサとして釣るといろいろな魚を釣ることができます。
ここでは、イワシ泳がせ釣り仕掛けと釣り方についてご紹介します。
イワシの泳がせ釣りの時期
イワシの泳がせ釣りの時期についてご紹介します。イワシを泳がせて釣るので、基本的にはイワシが回遊する時期がおすすめです。

相模湾では、イワシの泳がせ釣りが盛んに行われています。
ライトな泳がせ五目釣りです。
カサゴやメバル、ハタ類(アカハタやマハタなど)などの根魚が中心で、うまくいけばヒラメやスズキも釣れます。
釣りの時期としては、例年早春から初夏にかけて行われています。
特に、イワシの大群が回遊してくる2~3月がおすすめです。
こちらはあくまで一例です。
極端な話をすれば、生きたイワシを調達できる時期ならいつでも行えます。
もちろん、出てくれる船がないと釣りはできませんが・・・
どの地域で釣るのかや対象魚は何なのかによっても、おすすめの時期が異なります。
イワシの泳がせ釣りの仕掛け
イワシの泳がせ釣りの仕掛けについてご紹介します。仕掛けは次のとおりです。
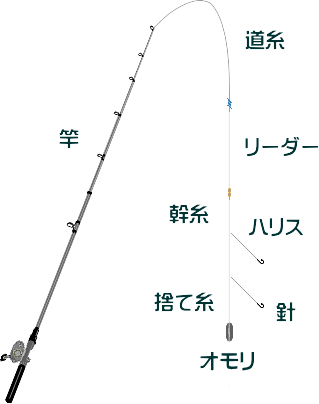
竿
竿はオモリ負荷20~60号前後のゲームロッドを使います。
6:4~7:3調子のものがおすすめです。
長さは2m前後が使いやすいです。
リール
リールは小型の両軸リールを使います。
道糸
道糸はPEの1.5~2号を使います。
リーダー
リーダーはフロロカーボンの5号を使います。
長さは1.5m前後です。
幹糸
幹糸はフロロカーボンの3~4号を使います。
ハリス
ハリスはフロロカーボンの2~3号を使います。
長さは50~60cmです。
ハリスの間隔は1~1.2mです。
捨て糸
捨て糸はフロロカーボンの2~2.5号です。
長さは20~30cmです。
針
針は、チヌ針の5~6号やイセアマの8号などを使います。
針の数は1~2本です。
ヒラメを狙うのなら、1本針がおすすめです。
オモリ
オモリは10~60号を使います。
船長からの指示に従います。
泳がせ釣りのイワシの付け方
泳がせ釣りのイワシの付け方についてご紹介します。エサはイワシですが、生きたカタクチイワシを使います。
7cm前後のものがよく使われます。
2本針の場合は、上針に大きめのエサを付けるとよいです。
良型のヒラメなどは上針に喰ってきやすいためです。
絶対ではありませんが・・・
イワシの下アゴから針を刺します。
そして、上アゴから針先を抜きます。
できるだけアゴの先端の中央に刺すようにします。
2本針仕掛けを使う場合、上の針からイワシを付けます。
エサ付けが終わったイワシは海に放ちます。
その後、下の針にイワシを付けてオモリを投入します。
イワシの泳がせの釣り方
イワシの泳がせの釣り方についてご紹介します。根魚を中心に狙うので、仕掛けを底まで沈めます。
着底すれば、30~40cm巻き上げます。
基本的には、そのままアタリを待ちます。
仕掛けを動かし過ぎると、逆に喰いが悪くなってしまいます。
底は岩礁帯であることが多いです。
そのため、適度に底を取り直さなければなりません。
この時、竿はできる限りゆっくり動かすようにします。
他にも、オモリを底に着けて釣る方法もあります。
着底後、ゼロテンで5秒ほどアタリを待ちます。
ゼロテンとは、道糸が張るか張らないかの状態をキープすることです。
アタリがなければ、竿先を大きく持ち上げてゆっくり落とし込んでいきます。
その後、ゼロテンでアタリを待ちます。
基本的にはこれを繰り返します。
エサのイワシが暴れ出せば、近くに魚が寄ってきた証拠です。
小さなアタリがあっても、まだ我慢です。
慌てて合わせると、すっぽ抜けてしまいます。
強く引き込めばしっかり合わせます。
周りは釣れているのに、自分だけが釣れないことがあります。
その場合は、エサのイワシが弱ってしまっている可能性があります。
イワシを交換するとよいです。
関連記事